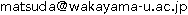

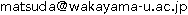
学歴
-
1994年-1997年
大阪大学大学院 基礎工学研究科 博士後期課程物理系情報工学分野
-
1992年-1994年
大阪大学大学院 基礎工学研究科 博士前期課程物理系専攻情報工学分野
-
1988年-1992年
関西大学 工学部
学位
-
博士(工学)
経歴
-
2023年04月-継続中
和歌山大学 社会インフォマティクス学環 教授
-
2006年04月-継続中
和歌山大学 システム工学部 准教授
-
2005年04月-2006年03月
和歌山大学 システム工学部 助教授
-
2004年04月-2005年03月
和歌山大学 工学部 講師
-
2000年04月-2004年03月
和歌山大学 システム工学部 助手
-
1998年-1999年
サスカチュワン大学 工学部 客員研究員
-
1997年04月-2000年03月
大阪大学 産業科学研究所 助手
所属学協会
-
-継続中
日本医療マネジメント学会
-
-継続中
電子情報通信学会
-
-継続中
人工知能学会
-
-継続中
教育システム情報学会
-
-継続中
日本医学看護学教育学会
-
-継続中
日本教育工学会
-
-継続中
日本医療教授システム学会
研究分野
-
人文・社会 / 教育工学
-
情報通信 / 学習支援システム
-
人文・社会 / 認知科学
研究シーズ
【学部】授業等(実験、演習、卒業論文指導、卒業研究、課題研究を含む)
-
2024年度 人工知能概論 連携展開科目
-
2024年度 人工知能の初歩 連携展開科目
-
2024年度 学環セミナーB 専門教育科目
-
2024年度 学環セミナーA 専門教育科目
-
2024年度 プロジェクト演習 専門教育科目
-
2024年度 基礎演習 専門教育科目
-
2024年度 情報プログラミング入門 専門教育科目
-
2024年度 論理的思考法概論 専門教育科目
-
2024年度 分析基礎演習 専門教育科目
-
2024年度 卒業研究(II・特) 専門教育科目
-
2024年度 卒業研究(II) 専門教育科目
-
2024年度 人工知能演習 専門教育科目
-
2024年度 知能情報学演習 専門教育科目
-
2024年度 人工知能 専門教育科目
-
2023年度 人工知能概論 連携展開科目
-
2023年度 人工知能の初歩 連携展開科目
-
2023年度 分析基礎演習 専門教育科目
-
2023年度 論理的思考法概論 専門教育科目
-
2023年度 基礎演習 専門教育科目
-
2023年度 知能情報学演習 専門教育科目
-
2023年度 卒業研究(II) 専門教育科目
-
2023年度 人工知能 専門教育科目
-
2023年度 人工知能演習 専門教育科目
-
2022年度 知能情報学メジャー体験演習 専門教育科目
-
2022年度 人工知能概論 連携展開科目
-
2022年度 人工知能の初歩 連携展開科目
-
2022年度 情報処理ⅠB 教養教育科目
-
2022年度 情報処理ⅠA 教養教育科目
-
2022年度 知能情報学演習 専門教育科目
-
2022年度 卒業研究 専門教育科目
-
2022年度 人工知能演習 専門教育科目
-
2022年度 人工知能 専門教育科目
-
2021年度 知能情報学メジャー体験演習 専門教育科目
-
2021年度 知能情報学演習 専門教育科目
-
2021年度 人工知能演習 専門教育科目
-
2021年度 人工知能 専門教育科目
-
2021年度 卒業研究 専門教育科目
-
2021年度 卒業研究 専門教育科目
-
2021年度 システム工学入門セミナー 専門教育科目
-
2021年度 情報処理ⅠB 教養教育科目
-
2021年度 人工知能概論 連携展開科目
-
2021年度 情報処理ⅠA 教養教育科目
-
2021年度 人工知能の初歩 連携展開科目
-
2020年度 人工知能概論 連携展開科目
-
2020年度 人工知能の初歩 連携展開科目
-
2020年度 情報処理ⅠB 教養教育科目
-
2020年度 情報処理ⅠA 教養教育科目
-
2020年度 卒業研究 専門教育科目
-
2020年度 卒業研究 専門教育科目
-
2020年度 人工知能演習 専門教育科目
-
2020年度 知能情報学演習 専門教育科目
-
2020年度 人工知能 専門教育科目
-
2020年度 知能情報学メジャー体験演習 専門教育科目
-
2019年度 知能情報学演習 専門教育科目
-
2019年度 知能システム演習 専門教育科目
-
2019年度 アルゴリズム演習Ⅰ 専門教育科目
-
2019年度 人工知能 専門教育科目
-
2019年度 情報処理Ⅰ 専門教育科目
-
2019年度 知能情報学メジャー体験演習 専門教育科目
-
2018年度 システム工学入門セミナー 専門教育科目
-
2018年度 情報処理Ⅰ 専門教育科目
-
2018年度 卒業研究 専門教育科目
-
2018年度 知能情報学演習 専門教育科目
-
2018年度 知能システム演習 専門教育科目
-
2018年度 アルゴリズム演習Ⅰ 専門教育科目
-
2018年度 プログラミング基礎Ⅱ 専門教育科目
-
2018年度 プログラミング基礎Ⅰ 専門教育科目
-
2018年度 人工知能 専門教育科目
-
2018年度 知能情報学メジャー体験演習 専門教育科目
-
2017年度 卒業研究 専門教育科目
-
2017年度 アルゴリズム演習Ⅰ 専門教育科目
-
2017年度 プログラミング基礎Ⅱ 専門教育科目
-
2017年度 プログラミング基礎Ⅰ 専門教育科目
-
2017年度 人工知能 専門教育科目
-
2017年度 情報処理Ⅰ 専門教育科目
-
2017年度 知能情報学メジャー体験演習 専門教育科目
-
2016年度 卒業研究 専門教育科目
-
2016年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2016年度 アルゴリズム演習Ⅰ 専門教育科目
-
2016年度 プログラミング基礎Ⅱ 専門教育科目
-
2016年度 システム工学自主演習Ⅴ 専門教育科目
-
2016年度 プログラミング基礎Ⅰ 専門教育科目
-
2016年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2016年度 人工知能 専門教育科目
-
2016年度 情報処理Ⅰ 専門教育科目
-
2015年度 卒業研究 専門教育科目
-
2015年度 情報処理Ⅰ 専門教育科目
-
2015年度 プログラミング基礎Ⅰ 専門教育科目
-
2015年度 システム工学入門セミナー 専門教育科目
-
2015年度 アルゴリズム演習Ⅰ 専門教育科目
-
2015年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2015年度 卒業研究 専門教育科目
-
2015年度 人工知能Ⅱ 専門教育科目
-
2015年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2015年度 プログラミング基礎Ⅱ 専門教育科目
-
2014年度 卒業研究 専門教育科目
-
2014年度 卒業研究 専門教育科目
-
2014年度 人工知能Ⅱ 専門教育科目
-
2014年度 アルゴリズム演習Ⅰ 専門教育科目
-
2014年度 プログラミング基礎Ⅱ 専門教育科目
-
2014年度 プログラミング基礎Ⅰ 専門教育科目
-
2014年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2014年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2014年度 情報通信システム入門セミナー 専門教育科目
-
2014年度 情報通信システムのしくみ 教養教育科目
-
2013年度 卒業研究 専門教育科目
-
2013年度 卒業研究 専門教育科目
-
2013年度 人工知能Ⅱ 専門教育科目
-
2013年度 アルゴリズム演習Ⅰ 専門教育科目
-
2013年度 プログラミング基礎Ⅱ 専門教育科目
-
2013年度 プログラミング基礎Ⅰ 専門教育科目
-
2013年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2013年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2013年度 情報通信システム入門セミナー 専門教育科目
-
2013年度 情報通信システムのしくみ 教養教育科目
-
2013年度 基礎教養セミナー 教養教育科目
-
2012年度 卒業研究 専門教育科目
-
2012年度 情報通信システム入門セミナー 専門教育科目
-
2012年度 情報通信システムのしくみ 教養教育科目
-
2012年度 プログラミング基礎Ⅰ 専門教育科目
-
2012年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2012年度 卒業研究 専門教育科目
-
2012年度 人工知能Ⅱ 専門教育科目
-
2012年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2012年度 プログラミング基礎Ⅱ 専門教育科目
-
2011年度 卒業研究 専門教育科目
-
2011年度 システム工学自主演習Ⅴ 専門教育科目
-
2011年度 システム工学自主演習Ⅱ 専門教育科目
-
2011年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2011年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2011年度 基礎教養セミナー 教養教育科目
-
2011年度 プログラミング基礎Ⅱ 専門教育科目
-
2011年度 プログラミング基礎Ⅰ 専門教育科目
-
2011年度 人工知能Ⅱ 専門教育科目
-
2011年度 情報通信システム入門セミナー 専門教育科目
-
2011年度 情報通信システムのしくみ 教養教育科目
-
2010年度 情報通信システムのしくみ 教養教育科目
-
2010年度 情報通信システム入門セミナー 専門教育科目
-
2010年度 プログラミング基礎Ⅰ 専門教育科目
-
2010年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2010年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2010年度 プログラミング基礎Ⅱ 専門教育科目
-
2010年度 人工知能Ⅱ 専門教育科目
-
2009年度 人工知能II 専門教育科目
-
2009年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2009年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2009年度 プログラミング基礎II 専門教育科目
-
2009年度 プログラミング基礎I 専門教育科目
-
2009年度 情報通信システム入門セミナー 専門教育科目
-
2009年度 卒業研究 専門教育科目
-
2009年度 情報通信のしくみ 教養教育科目
-
2008年度 卒業研究(情報通信システム学科) 専門教育科目
-
2008年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2008年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2008年度 プログラミング基礎II 専門教育科目
-
2008年度 プログラミング基礎I 専門教育科目
-
2008年度 情報通信システム入門セミナー 専門教育科目
-
2008年度 卒業研究 専門教育科目
-
2007年度 情報通信システム演習 専門教育科目
-
2007年度 知識システム演習 専門教育科目
-
2007年度 プログラミング基礎II 専門教育科目
-
2007年度 プログラミング基礎I 専門教育科目
-
2007年度 情報通信システム入門セミナー 専門教育科目
-
2007年度 卒業研究 専門教育科目
【学部】サテライト科目
-
2024年度 未来都市を創造する 連携展開科目
【学部】自主演習
-
2018年度 人工知能による道案内システムの開発
-
2017年度 人工知能による道案内システムの開発
-
2011年度 ソーシャルネットワークシステムの分析
-
2010年度 述語論理
-
2009年度 C言語によるゲーム制作
-
2009年度 ゲーム制作
-
2008年度 C言語によるゲーム制作
-
2007年度 ゲーム作成の基礎練習
【大学院】授業等
-
2024年度 システム工学グローバル講究Ⅱ 博士後期
-
2024年度 システム工学グローバル講究Ⅱ 博士後期
-
2024年度 システム工学グローバル講究Ⅰ 博士後期
-
2024年度 システム工学グローバル講究Ⅰ 博士後期
-
2024年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2024年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2024年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2024年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2024年度 システム工学特別講究Ⅰ 博士後期
-
2024年度 システム工学特別講究Ⅰ 博士後期
-
2024年度 システム工学研究ⅡB 博士前期
-
2024年度 システム工学研究ⅡA 博士前期
-
2024年度 システム工学研究ⅠB 博士前期
-
2024年度 システム工学研究ⅠA 博士前期
-
2024年度 知識工学 博士前期
-
2024年度 システム工学講究ⅡB 博士前期
-
2024年度 システム工学講究ⅡA 博士前期
-
2024年度 システム工学講究ⅠB 博士前期
-
2024年度 システム工学講究ⅠA 博士前期
-
2023年度 システム工学講究ⅠA(知能科学) 博士前期
-
2023年度 システム工学講究ⅠB(知能科学) 博士前期
-
2023年度 システム工学講究ⅡA(知能科学) 博士前期
-
2023年度 システム工学講究ⅡB(知能科学) 博士前期
-
2023年度 知識工学 博士前期
-
2023年度 システム工学研究ⅠA(知能科学) 博士前期
-
2023年度 システム工学研究ⅠB(知能科学) 博士前期
-
2023年度 システム工学研究ⅡA(知能科学) 博士前期
-
2023年度 システム工学研究ⅡB(知能科学) 博士前期
-
2023年度 システム工学特別講究Ⅰ 博士後期
-
2023年度 システム工学特別講究Ⅰ 博士後期
-
2023年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2023年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2023年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2023年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2023年度 システム工学グローバル講究Ⅰ 博士後期
-
2023年度 システム工学グローバル講究Ⅰ 博士後期
-
2023年度 システム工学グローバル講究Ⅱ 博士後期
-
2023年度 システム工学グローバル講究Ⅱ 博士後期
-
2022年度 システム工学グローバル講究Ⅱ 博士後期
-
2022年度 システム工学グローバル講究Ⅰ 博士後期
-
2022年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2022年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2022年度 システム工学特別講究Ⅰ 博士後期
-
2022年度 システム工学研究ⅡB 博士前期
-
2022年度 システム工学研究ⅡA 博士前期
-
2022年度 システム工学研究ⅠB 博士前期
-
2022年度 システム工学研究ⅠA 博士前期
-
2022年度 知識工学 博士前期
-
2022年度 システム工学講究ⅡB 博士前期
-
2022年度 システム工学講究ⅡA 博士前期
-
2022年度 システム工学講究ⅠB 博士前期
-
2022年度 システム工学講究ⅠA 博士前期
-
2021年度 システム工学グローバル講究Ⅱ 博士後期
-
2021年度 システム工学グローバル講究Ⅰ 博士後期
-
2021年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2021年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2021年度 システム工学特別講究Ⅰ 博士後期
-
2021年度 システム工学研究ⅡB 博士前期
-
2021年度 システム工学研究ⅡA 博士前期
-
2021年度 システム工学研究ⅠB 博士前期
-
2021年度 システム工学研究ⅠA 博士前期
-
2021年度 知識工学 博士前期
-
2021年度 システム工学講究ⅡB 博士前期
-
2021年度 システム工学講究ⅡA 博士前期
-
2021年度 システム工学講究ⅠB 博士前期
-
2021年度 システム工学講究ⅠA 博士前期
-
2020年度 システム工学グローバル講究Ⅱ 博士後期
-
2020年度 システム工学グローバル講究Ⅰ 博士後期
-
2020年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2020年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2020年度 システム工学特別講究Ⅰ 博士後期
-
2020年度 システム工学研究ⅡB 博士前期
-
2020年度 システム工学研究ⅡA 博士前期
-
2020年度 システム工学研究ⅠB 博士前期
-
2020年度 システム工学研究ⅠA 博士前期
-
2020年度 知識工学 博士前期
-
2020年度 システム工学講究ⅡB 博士前期
-
2020年度 システム工学講究ⅡA 博士前期
-
2020年度 システム工学講究ⅠB 博士前期
-
2020年度 システム工学講究ⅠA 博士前期
-
2019年度 知識工学 博士前期
-
2019年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2019年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2019年度 システム工学講究ⅡB 博士前期
-
2019年度 システム工学講究ⅡA 博士前期
-
2019年度 システム工学講究ⅠB 博士前期
-
2019年度 システム工学講究ⅠA 博士前期
-
2019年度 システム工学研究ⅡB 博士前期
-
2019年度 システム工学研究ⅡA 博士前期
-
2019年度 システム工学研究ⅠB 博士前期
-
2019年度 システム工学研究ⅠA 博士前期
-
2018年度 システム工学グローバル講究Ⅱ 博士後期
-
2018年度 システム工学グローバル講究Ⅱ 博士後期
-
2018年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2018年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2018年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2018年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2018年度 システム工学研究ⅡB 博士前期
-
2018年度 システム工学研究ⅡA 博士前期
-
2018年度 システム工学研究ⅠB 博士前期
-
2018年度 システム工学研究ⅠA 博士前期
-
2018年度 システム工学講究ⅡB 博士前期
-
2018年度 システム工学講究ⅡA 博士前期
-
2018年度 システム工学講究ⅠB 博士前期
-
2018年度 システム工学講究ⅠA 博士前期
-
2018年度 知識工学 博士前期
-
2017年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2017年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2017年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2017年度 システム工学特別講究Ⅱ 博士後期
-
2017年度 システム工学研究ⅡB 博士前期
-
2017年度 システム工学研究ⅡA 博士前期
-
2017年度 システム工学研究ⅠB 博士前期
-
2017年度 システム工学研究ⅠA 博士前期
-
2017年度 知識工学 博士前期
-
2017年度 システム工学講究ⅡB 博士前期
-
2017年度 システム工学講究ⅡA 博士前期
-
2017年度 システム工学講究ⅠB 博士前期
-
2017年度 システム工学講究ⅠA 博士前期
-
2016年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2016年度 システム工学特別研究 博士後期
-
2016年度 システム工学特別講究Ⅰ 博士後期
-
2016年度 システム工学特別講究Ⅰ 博士後期
-
2016年度 システム工学研究ⅡB 博士前期
-
2016年度 システム工学研究ⅡA 博士前期
-
2016年度 システム工学研究ⅠB 博士前期
-
2016年度 システム工学研究ⅠA 博士前期
-
2016年度 システム工学講究ⅡB 博士前期
-
2016年度 システム工学講究ⅡA 博士前期
-
2016年度 システム工学講究ⅠB 博士前期
-
2016年度 システム工学講究ⅠA 博士前期
-
2016年度 知識工学 博士前期
-
2015年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2015年度 システム工学特別研究 その他
-
2015年度 システム工学講究ⅡA その他
-
2015年度 システム工学講究ⅠA その他
-
2015年度 システム工学研究ⅡA その他
-
2015年度 システム工学研究ⅠA その他
-
2015年度 知識工学 その他
-
2015年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2015年度 システム工学特別研究 その他
-
2015年度 システム工学講究ⅡB その他
-
2015年度 システム工学講究ⅠB その他
-
2015年度 システム工学研究ⅡB その他
-
2015年度 システム工学研究ⅠB その他
-
2014年度 システム工学特別研究 その他
-
2014年度 システム工学特別研究 その他
-
2014年度 システム工学特別講究Ⅱ その他
-
2014年度 システム工学特別講究Ⅱ その他
-
2014年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2014年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2014年度 システム工学研究ⅡB その他
-
2014年度 システム工学研究ⅡA その他
-
2014年度 システム工学研究ⅠB その他
-
2014年度 システム工学研究ⅠA その他
-
2014年度 知識工学 その他
-
2014年度 システム工学講究ⅡB その他
-
2014年度 システム工学講究ⅡA その他
-
2014年度 システム工学講究ⅠB その他
-
2014年度 システム工学講究ⅠA その他
-
2013年度 システム工学特別研究 その他
-
2013年度 システム工学特別研究 その他
-
2013年度 システム工学特別講究Ⅱ その他
-
2013年度 システム工学特別講究Ⅱ その他
-
2013年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2013年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2013年度 システム工学研究ⅡB その他
-
2013年度 システム工学研究ⅡA その他
-
2013年度 システム工学研究ⅠB その他
-
2013年度 システム工学研究ⅠA その他
-
2013年度 知識工学 その他
-
2013年度 システム工学講究ⅡB その他
-
2013年度 システム工学講究ⅡA その他
-
2013年度 システム工学講究ⅠB その他
-
2013年度 システム工学講究ⅠA その他
-
2012年度 システム工学特別講究Ⅱ その他
-
2012年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2012年度 システム工学特別研究 その他
-
2012年度 システム工学講究ⅡA その他
-
2012年度 システム工学講究ⅠA その他
-
2012年度 システム工学研究ⅡA その他
-
2012年度 システム工学研究ⅠA その他
-
2012年度 知識工学 その他
-
2012年度 システム工学特別講究Ⅱ その他
-
2012年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2012年度 システム工学特別研究 その他
-
2012年度 システム工学講究ⅡB その他
-
2012年度 システム工学講究ⅠB その他
-
2012年度 システム工学研究ⅡB その他
-
2012年度 システム工学研究ⅠB その他
-
2011年度 システム工学研究ⅡB その他
-
2011年度 システム工学研究ⅡA その他
-
2011年度 システム工学研究ⅠB その他
-
2011年度 システム工学研究ⅠA その他
-
2011年度 システム工学特別研究 その他
-
2011年度 システム工学特別研究 その他
-
2011年度 システム工学講究(ⅠB・ⅡB) その他
-
2011年度 システム工学講究(ⅠA・ⅡA) その他
-
2011年度 システム工学特別講究Ⅱ その他
-
2011年度 システム工学特別講究Ⅱ その他
-
2011年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2011年度 システム工学特別講究Ⅰ その他
-
2011年度 知識工学 その他
-
2010年度 システム工学講究IA・IB 博士前期
-
2010年度 システム工学講究IIA・IIB 博士前期
-
2010年度 システム工学研究IA・IB 博士前期
-
2010年度 システム工学研究IIA・IIB 博士前期
-
2010年度 知識工学 博士前期
-
2009年度 知識工学 博士前期
-
2009年度 システム工学研究IIA・IIB 博士前期
-
2009年度 システム工学研究IA・IB 博士前期
-
2009年度 システム工学講究IIA・IIB 博士前期
-
2009年度 システム工学講究IA・IB 博士前期
-
2008年度 知識工学 博士前期
-
2008年度 システム工学研究IIA・IIB 博士前期
-
2008年度 システム工学研究IA・IB 博士前期
-
2008年度 システム工学講究IIA・IIB 博士前期
-
2008年度 システム工学講究IA・IB 博士前期
-
2007年度 知識工学 博士前期
-
2007年度 システム工学研究II 博士前期
-
2007年度 システム工学研究I 博士前期
-
2007年度 システム工学講究II 博士前期
-
2007年度 システム工学講究I 博士前期
【大学院】サテライト科目
-
2020年度 現代社会における知的情報通信システム その他
-
2013年度 情報通信システム概論 その他
受賞(教育活動に関するもの)
-
2019年度 グッドレクチャー賞 2019年3月19日 システム工学部 国内
研究キーワード
-
経験学習
-
教育工学
-
メタ思考
論文
-
Analysis of Frontal Cerebral Blood Flow Changes in Hand Grip Force Adjustment Skill Learning.
Hirokazu Miura, Masahiro Hakoda, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION & ENGINEERING SYSTEMS (KES 2019) ( ELSEVIER ) 159 2224 - 2231 2019年 [査読有り]
-
Analysis of brain activity in distance recognition.
Shohei Matsui, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Masato Soga, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION & ENGINEERING SYSTEMS (KES-2018) ( ELSEVIER SCIENCE BV ) 126 2058 - 2064 2018年 [査読有り]
-
Measurement of Brain Activity on Force Adjustment Skill Acquisition by using EEG.
Masahiro Hakoda, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Fumitaka Uchio, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION & ENGINEERING SYSTEMS ( ELSEVIER SCIENCE BV ) 112 1273 - 1280 2017年 [査読有り]
-
Analysis of the Cerebral Blood Flow Affected by Brand Impressions of the Products.
Riku Nakamura, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION & ENGINEERING SYSTEMS: PROCEEDINGS OF THE 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE KES-2016 ( ELSEVIER SCIENCE BV ) 96 ( C ) 1748 - 1755 2016年 [査読有り]
-
Analysis of Cerebral Blood Flow in Imagination of Moving Object.
Daiki Kurematsu, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION & ENGINEERING SYSTEMS: PROCEEDINGS OF THE 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE KES-2016 ( ELSEVIER SCIENCE BV ) 96 1756 - 1763 2016年 [査読有り]
-
Design of a System of Thinking Training through Writing
Nakajima, T, Matsuda, N, Cui, L, Tanaka. K, Ikeda, M
Proceedings of the 11th International Conference on Knowledge Management ( The Association International Council on Knowledge Management ) 169 - 177 2015年11月 [査読有り]
-
A Collaborative Learning Program Focused on Belief Conflict
Ogawa, T, Matsuda, N, Seta, K, Ikeda, M
Proceedings of the 11th International Conference on Knowledge Management ( International Conference on Knowledge Management ) 207 - 216 2015年11月 [査読有り]
-
Noriyuki Matsuda, Hisashi Ogawa, Tsukasa Hirashima, Hirokazu Taki (担当区分: 筆頭著者 )
In: Yamamoto S. (eds) Human Interface and the Management of Information. Information and Knowledge in Context. HIMI 2015. Lecture Notes in Computer Science ( Springer ) 9173 362 - 369 2015年07月 [査読有り]
-
The Analysis of the Brain State Measuring by NIRS-based BMI in Answering yes-no Questions.
Kosuke Tanino, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION & ENGINEERING SYSTEMS 19TH ANNUAL CONFERENCE, KES-2015 ( ELSEVIER SCIENCE BV ) 60 1233 - 1239 2015年 [査読有り]
-
Noriyuki Matsuda, Hisashi Ogawa, Tsukasa Hirashima, Hirokazu Taki (担当区分: 筆頭著者 )
Res. Pract. Technol. Enhanc. Learn. ( Springer ) 10 ( 1 ) 6 - 6 2015年 [査読有り]
-
Reviewing system of writing for hospital nurses
Hideyuki KANO, Hirotaka NISHIYAMA, Koji TANAKA, Liang CUI, Noriyuki MATSUDA, Hirokazu MIURA, Mitsuru IKEDA, Hirokazu TAKI
Proc. of The 22nd International Conference on Computers in Education ( Asia-Pacific Society for Computers in Education ) WIPPC1‐ 01 2014年11月 [査読有り]
-
Using Ontology for Representing Role Change Design in Nursing Service Thinking Education
Chen, W, Cui, L, Tanaka, K, Nishiyama, H, Matsuda, N, Ikeda, M
Proceedings of the 22th International Conference on Computers in Education ( Asia-Pacific Society for Computers in Education ) W13‐03 2014年11月 [査読有り]
-
Classification of Haptic Tasks based on Electroencephalogram Frequency Analysis.
Hirokazu Miura, Junki Kimura, Noriyuki Matsuda, Masato Soga, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION & ENGINEERING SYSTEMS 18TH ANNUAL CONFERENCE, KES-2014 ( ELSEVIER SCIENCE BV ) 35 1270 - 1277 2014年 [査読有り]
-
Classification by EEG Frequency Distribution in Imagination of Directions.
Yuki Seto, Shumpei Ako, Keijiro Sakagami, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Masato Soga, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION & ENGINEERING SYSTEMS 18TH ANNUAL CONFERENCE, KES-2014 ( ELSEVIER SCIENCE BV ) 35 1300 - 1306 2014年 [査読有り]
-
A Method of Sharing the Intention of Reviewing in Writing-Training for Nurses
Hideyuki Kanou, Noriyuki Matsuda, Cui Liang, Mituru Ikeda Yuu Okamuro, Kazuhisa Seta, Hirokazu Taki
Proc. of 21st International Conference on Computers in Education 983 - 989 2013年11月 [査読有り]
-
Electroencephalogram Analysis of Pseudo-Haptic Application for Skill Learning Support System
Hirokazu MIURA, Keijiro SAKAGAMI, Yuki SETO, Shumpei AKO, Hirokazu TAKI, Noriyuki MATSUDA, Masato SOGA
21st International Conference on Computers in Education,3rd Workshop on SKill Analysis, learning or Teaching of Skills, Learning Environments or Training Environments for Skills ( Asia Pacific Society for Computers in Education ) W5-04 2013年11月 [査読有り]
-
Analysis of Brain State in Imaging Directions by Using EEG
Seto Yuki, Ako Shumpei, Miura Hirokazu, Matsuda Noriyuki, Taki Hirokazu
生体医工学 ( Japanese Society for Medical and Biological Engineering ) 51 R - 192-R-192 2013年
-
Kazuhisa Seta, Liang Cui, Mitsuru Ikeda, Noriyuki Matsuda, Masahiko Okamoto
Int. J. Knowl. Web Intell. ( Inderscience Publishers ) 4 ( 2/3 ) 217 - 237 2013年 [査読有り]
-
思考外化と知識共創によるメタ認知スキル育成プログラム ―大学初年次生を対象として―
瀬田 和久, 崔 亮, 池田 満, 松田 憲幸, 岡本 真彦
教育システム情報学会誌 ( 教育システム情報学会 ) 30 ( 1 ) 77 - 91 2013年 [査読有り]
-
Prologによる解法知識を用いた誤答解説文付き多肢選択問題の生成
小川 修史, 松田 憲幸, 平嶋 宗, 瀧 寛和
教育システム情報学会誌 ( 教育システム情報学会 ) 30 ( 2 ) 139 - 147 2013年 [査読有り]
-
Meta-cognitive skill training by serializing self-dialogue and discussion processes
Kazuhisa Seta, Liang Cui, Mitsuru Ikeda, Noriyuki Matsuda, Masahiko Okamoto
Workshop Proceedings of the 20th International Conference on Computers in Education, ICCE 2012 175 - 183 2012年
-
Kazuhisa Seta, Liang Cui, Mitsuru Ikeda, Noriyuki Matsuda
In: Cerri S.A., Clancey W.J., Papadourakis G., Panourgia K. (eds) Intelligent Tutoring Systems. ITS 2012. Lecture Notes in Computer Science ( Springer Berlin Heidelberg ) 7315 683 - 684 2012年 [査読有り]
-
Message reply method by making use of node location advertisement in VANET.
Hirokazu Miura, Muneyuki Noguchi, Noriyuki Matsuda, Masato Soga, Hirokazu Taki
ADVANCES IN KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS ( IOS PRESS ) 243 941 - 952 2012年 [査読有り]
-
Kazuhisa Seta, Liang Cui, Mitsuru Ikeda, Noriyuki Matsuda
ADVANCES IN KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS ( IOS PRESS ) 243 1071 - 1080 2012年 [査読有り]
-
Sizhi: Self-Dialogue Training through Reflective Case-Writing for Medical Service Education
Wei CHEN, Masaki FUJII, Liang CUI, Mitsuru IKEDA, Kazuhis SETA, Noriyuki MATSUDA
Mohd Ayub A. F. et al. (Eds.) (2011). Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Computers in Education ( Asia-Pacific Society for Computers in Education ) 551 - 558 2011年11月 [査読有り]
-
A Model of Collaborative Learning for Improving The Quality of Medical Services
Cui Liang, Kamiyama Motoyuki, Matsuda Noriyuki, Seta Kazuhisa, Ikeda Mitsuru
The 6th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems 112 - 121 2011年10月 [査読有り]
-
Knowledge Externalization Based on Differences of Solutions for Automatic generation of Multiple-choice Question
Hisashi Ogawa, Hiroki Kobayashi, Noriyuki Matsuda, Tsukasa Hirashima, Hirokazu Taki
T. Hirashima et al. (Eds.) (2011) Proceedings of the 19th International Conference on Computers in Education. ( Asia-Pacific Society for Computers in Education ) 2011年01月 [査読有り]
-
A Study on Navigation System for Pedestrians Based on Street Illuminations.
Hirokazu Miura, Syujo Takeshima, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki
In: König A., Dengel A., Hinkelmann K., Kise K., Howlett R.J., Jain L.C. (eds) Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems. KES 2011. Lecture Notes in Computer Science ( Springer, Berlin, Heidelberg. ) 6883 49 - 55 2011年 [査読有り]
-
西田 好宏, 小倉 一孝, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 安部 憲広
ヒューマンインタフェース学会論文誌 ( ヒューマンインタフェース学会 ) 12 ( 3 ) 289 - 296 2010年08月 [査読有り]
-
A Technique for Error Awareness in Pencil Drawing
Noriyuki MATSUDA, Tsukasa HIRASHIMA, Tomoya HORIGUCHI, Hirokazu TAKI (担当区分: 筆頭著者 )
S. L. Wong et al. (Eds.) (2010). Proceedings of the 18th International Conference on Computers in Education ( Asia-Pacific Society for Computers in Education ) 275 - 279 2010年04月 [査読有り]
-
Message Ferry Route Design Based on Clustering for Sparse Ad hoc Networks.
Hirokazu Miura, Daisuke Nishi, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED AND INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT II ( SPRINGER-VERLAG BERLIN ) 6277 637 - 644 2010年 [査読有り]
-
Real time interpolation of haptic information using case base
Takayuki Toki, Hirokazu Taki, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Masato Soga, Norihiro Abe
Proceedings of the 15th International Symposium on Artificial Life and Robotics, AROB 15th'10 1006 - 1009 2010年
-
Ontology-based Annotations for Test Interpretation and Scoring
Matsuda, N, Kanev, K, Hirashima, T, Taki, H (担当区分: 筆頭著者 )
In Proceedings of the 12th Int. Conf. on Humans and Computers HC'09 ( Human and Computers ) 118 - 122 2009年12月 [査読有り]
-
松田 憲幸, 高木 佐恵子, 曽我 真人, 堀口 知也, 平嶋 宗, 瀧 寛和, 吉本 富士市 (担当区分: 筆頭著者 )
電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム = The IEICE transactions on information and systems (Japanese edition) ( 電子情報通信学会 ) 91 ( 2 ) 324 - 332 2008年02月 [査読有り]
-
Analysis of Continuous Tracks of Online Aerial Handwritten Character Recognition.
Kazutaka Ogura, Yoshihiro Nishida, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki, Norihiro Abe
KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 3, PROCEEDINGS ( SPRINGER-VERLAG BERLIN ) 5179 687 - 694 2008年 [査読有り]
-
Ubiquitous Earthquake Observation System Using Wireless Sensor Devices.
Hirokazu Miura, Yosuke Shimazaki, Noriyuki Matsuda, Fumitaka Uchio, Koji Tsukada, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 3, PROCEEDINGS ( SPRINGER-VERLAG BERLIN ) 5179 673 - 679 2008年 [査読有り]
-
Interactive Learning Environment for Drawing Skill Based on Perspective.
Yoshitake Shojiguchi, Masato Soga, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki
KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 3, PROCEEDINGS ( SPRINGER-VERLAG BERLIN ) 5179 695 - 700 2008年 [査読有り]
-
デッサン描画中に描画領域に依存したアドバイスを提示するデッサン学習支援環境
曽我 真人, 松田 憲幸, 瀧 寛和
人工知能学会論文誌 ( 一般社団法人 人工知能学会 ) 23 ( 3 ) 96 - 104 2008年 [査読有り]
-
自閉症者の認知発達段階に特化した学習者モデルに基づくディジタル教材製作支援
小川 修史, 松田 憲幸, 三浦 浩一, 瀧 寛和
電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム = The IEICE transactions on information and systems (Japanese edition) ( 一般社団法人電子情報通信学会 ) 90 ( 12 ) 3192 - 3200 2007年12月 [査読有り]
-
学習者の腕動作のアニメーション機能を持つデッサン腕動作リアルタイム診断助言システムの構築
曽我 真人, 前野 浩孝, 古賀 俊廣, 和田 隆人, 松田 憲幸, 高木 佐恵子, 瀧 寛和, 吉本 富士市
教育システム情報学会誌 ( 教育システム情報学会誌 ) 24 ( 4 ) 311 - 322 2007年10月 [査読有り]
-
Sketch Drawing Support Environment based on Recognition Skill Analysis
Masato Soga, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki
Proceedings of the 1st International Symposium on Skill Science 2007 (ISSS'07) 61 - 67 2007年09月 [査読有り]
-
Sketch Learning Environment Based on Drawing Skill Analysis.
Masato Soga, Noriyuki Matsuda, Saeko Takagi, Hirokazu Taki, Fujiichi Yoshimoto
KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS: KES 2007 - WIRN 2007, PT III, PROCEEDINGS ( SPRINGER-VERLAG BERLIN ) 4694 1073 - 1080 2007年 [査読有り]
-
Indoor Localization for Mobile Node Based on RSSI.
Hirokazu Miura, Kazuhiko Hirano, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki, Norihiro Abe, Satoshi Hori
KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS: KES 2007 - WIRN 2007, PT III, PROCEEDINGS ( SPRINGER-VERLAG BERLIN ) 4694 1065 - 1072 2007年 [査読有り]
-
Hisashi Ogawa, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Miura, Hirokazu Taki
SUPPORTING LEARNING FLOW THROUGH INTEGRATIVE TECHNOLOGIES ( IOS PRESS ) 162 105 - 108 2007年 [査読有り]
-
An Interpretation Method for Classification Trees in Bio-data Mining.
Shigeki Kozakura, Hisashi Ogawa, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki, Satoshi Hori, Norihiro Abe
KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 2, PROCEEDINGS ( SPRINGER-VERLAG BERLIN ) 4252 620 - 627 2006年 [査読有り]
-
Adequate RSSI Determination Method by Making Use of SVM for Indoor Localization.
Hirokazu Miura, Junichi Sakamoto, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki, Noriyuki Abe, Satoshi Hori
KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 2, PROCEEDINGS ( SPRINGER-VERLAG BERLIN ) 4252 628 - 636 2006年 [査読有り]
-
Improvement of relief algorithm to prevent inpatient's downfall accident with nightvision CCD camera
Noriyuki Matsuda, Takeshi Yamamoto, Shinobu On, Kumiko Mori, Yoshiko Kounose, tsuko Maeda, Hirokazu Miura, Hirokazu Taki, Satoshi Hori, Noriyuki Abe (担当区分: 筆頭著者 )
Proc. SPIE 6051, Optomechatronic Machine Vision, 605118 2005年12月 [査読有り]
-
A Sketch Learning Support System with Automatic Diagnosis and Advice
Tomohiro IWAKI, Tatsuya TSUJI, Hirotaka MAENO, Masato SOGA, Noriyuki MATSUDA, Saeko TAKAGI, Hirokazu TAKI, Fujiichi YOSHIMOTO
The 13th International Conference on Computers in Education (ICCE2005) 977 - 979 2005年11月 [査読有り]
-
Tutoring System for Basic Sketching
Saeko Takagi, Noriyuki Matsuda, Masato Soga, Hirokazu Taki, Fujiichi Yoshimoto
The 3rd nternational Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Australasia and Southeast Asia (GRAPHITE2005) Poster Session No. 19 2005年11月 [査読有り]
-
Support System for Basic Sketch Skill Learning
Saeko Takagi, Noriyuki Matsuda, Masato Soga, Hirokazu Taki, Fujiichi Yoshimoto
Proc. of NICOGRAPH International 2005 61 - 66 2005年06月 [査読有り]
-
Constructive Induction-Based Clustering Method for Ubiquitous Computing Environments.
Takeshi Yamamoto, Hirokazu Taki, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Miura, Satoshi Hori, Noriyuki Abe
In: Khosla R., Howlett R.J., Jain L.C. (eds) Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. KES 2005. Lecture Notes in Computer Science ( Springer, Berlin, Heidelberg ) 3684 136 - 142 2005年 [査読有り]
-
Indoor Location Determination Using a Topological Model.
Junichi Sakamoto, Hirokazu Miura, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki, Noriyuki Abe, Satoshi Hori
KES'05: Proceedings of the 9th international conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems - Volume Part IV ( Springer ) 143 - 149 2005年 [査読有り]
-
Real Time Advice System for Sketch Learning.
Hirotaka Maeno, Tomohiro Iwaki, Masato Soga, Noriyuki Matsuda, Saeko Takagi, Hirokazu Taki, Fujiichi Yoshimoto
TOWARDS SUSTAINABLE AND SCALABLE EDUCATIONAL INNOVATIONS INFORMED BY LEARNING SCIENCES ( IOS PRESS ) 133 795 - 798 2005年 [査読有り]
-
Design of an Authoring System Based on a Student Model for Digital Educational Content for Autistic People
Hisashi Ogawa, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Miura, Hirokazu Taki, Norihiro Abe, Satoshi Hori
Proceeding of International Conference on Computers in Education 2004 1697 - 1706 2004年12月 [査読有り]
-
Design of Semantic Web Application based on Physical State Model of Products
Noriyuki Matsuda, Michiyasu Hiramatsu, Hirokazu Taki, Satoshi Hori, Norihiro Abe (担当区分: 筆頭著者 )
3rd International Semantic Web Conference (ISWC2004) Poster abstracts 37 - 38 2004年11月 [査読有り]
-
Design and Evaluation of Automated Integration System for a Programming Class
Noriyuki Matsuda, Katsuyuki Harada, Hirokazu Taki (担当区分: 筆頭著者 )
Proceeding of International Conference on Computers in Education 2111 - 2113 2004年11月 [査読有り]
-
Design of an Automated Record Integration System for a Programming Exercise Class
松田 憲幸 (担当区分: 筆頭著者 )
The 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies ( IEEE Computer Society ) 862 - 863 2004年09月 [査読有り]
-
Automated Record Integration System For a Class
Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki (担当区分: 筆頭著者 )
Proceedings of the IADIS International Conference (e-Society 2004) 403 - 408 2004年07月 [査読有り]
-
Advice Recording Method for a Lesson with Computers.
Katsuyuki Harada, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Miura, Hirokazu Taki, Satoshi Hori, Norihiro Abe
In: Negoita M.G., Howlett R.J., Jain L.C. (eds) Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. KES 2004. Lecture Notes in Computer Science ( Springer, Berlin, Heidelberg ) 3214 181 - 187 2004年 [査読有り]
-
Construction of Conscious Model Using Reinforcement Learning.
Masafumi Kozuma, Hirokazu Taki, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Miura, Satoshi Hori, Norihiro Abe
In: Negoita M.G., Howlett R.J., Jain L.C. (eds) Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. KES 2004. Lecture Notes in Computer Science ( Springer ) 3214 175 - 180 2004年 [査読有り]
-
Tutoring System for Pencil Drawing Discipline
Noriyuki Matsuda, Saeko Takagi, Masato Soga, Tsukasa Hirashima, Tomoya Horiguchi, Hirokazu Taki, Takashi Shima, Fujiichi Yoshimoto (担当区分: 筆頭著者 )
Proceeding of International Conference on Computers in Education 2003 1163 - 1170 2003年11月 [査読有り]
-
高木 佐恵子, 松田 憲幸, 曽我 真人, 瀧 寛和, 志磨 隆, 吉本 富士市
画像電子学会誌 ( 画像電子学会 ) 32 ( 4 ) 386 - 396 2003年07月 [査読有り]
-
Ontology-Based Medical Information Service System.
Hirokazu Taki, Noriyuki Matsuda, Michiyasu Hiramatsu, Yuki Naito, Jiro Nakajima, Tadashi Nakamura, Akihisa Imagawa, Yuji Matsuzawa, Norihiro Abe, Satoshi Hori
Lecture Notes in Computer Science ( Springer Berlin Heidelberg ) 2774 358 - 365 2003年 [査読有り]
-
An Educational Tool for Basic Techniques in Beginner's Pencil Drawing.
Saeko Takagi, Noriyuki Matsuda, Masato Soga, Hirokazu Taki, Takashi Shima, Fujiichi Yoshimoto
Proceedings Computer Graphics International 2003 ( IEEE Comput. Soc ) 288 - 293 2003年 [査読有り]
-
A learning support system for beginners in pencil drawing.
Saeko Takagi, Noriyuki Matsuda, Masato Soga, Hirokazu Taki, Takashi Shima, Fujiichi Yoshimoto
Proceedings of the 1st international conference on Computer graphics and interactive techniques in Austalasia and South East Asia - GRAPHITE '03 ( ACM Press ) 281 - 282 2003年 [査読有り]
-
Context-sensitive filtering for the web.
Noriyuki Matsuda, Tsukasa Hirashima, Toyohiro Nomoto, Hirokazu Taki, Jun'ichi Toyoda (担当区分: 筆頭著者 )
Web Intell. Agent Syst. 1 ( 3-4 ) 249 - 257 2003年 [査読有り]
-
Proposal of an Automated Record Integration System for a Programming Exercise Class.
Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki (担当区分: 筆頭著者 )
International Conference on Computers in Education, 2002. Proceedings. ( IEEE Comput. Soc ) 1 193 - 194 2002年12月 [査読有り]
-
初心者のための鉛筆デッサン学習支援システム
高木 佐恵子, 松田 憲幸, 曽我 真人, 瀧 寛和, 吉本 富士市
芸術科学会 第18回NICOGRAPH論文コンテスト 論文集 127 - 132 2002年10月 [査読有り]
-
Webブラウジングを対象としたページ分割による情報フィルタリング手法の提案と評価
松田 憲幸, 野本 豊裕, 平嶋 宗, 豊田 順一 (担当区分: 筆頭著者 )
システム制御情報学会論文誌 ( 一般社団法人 システム制御情報学会 ) 15 ( 4 ) 175 - 183 2002年04月 [査読有り]
-
The Proposal of the Technique of Error Visualization for a Learner's Pencil Drawing.
Nobuyuki Kajimoto, Noriyuki Matsuda, Hirokazu Taki, Masato Soga, Saeko Takagi, Fujiichi Yoshimoto, Takashi Shima
International Conference on Computers in Education, 2002. Proceedings. ( IEEE Comput. Soc ) 1 153 - 157 2002年 [査読有り]
-
Design of an error visualization tool to compare data flow with algorithms of simple recursion
松田 憲幸, 平嶋 宗, 瀧 寛和
Proc. of ICCE2001 250 - 253 2001年11月 [査読有り]
-
Context-Sensitive Filtering for Browsing on the Web Pages.
Tsukasa Hirashima, Toyohiro Nomoto, Noriyuki Matsuda, Jun'ichi Toyoda
Proc. of WebNet 1999 ( AACE ) 1294 - 1295 1999年 [査読有り]
-
The Design of Recursive Programming Exercises Based on Behavior of Programs
N. Matsuda, A. Kashihara, T. Hirashima, J. Toyoda (担当区分: 筆頭著者 )
Proc. of ED-MEDIA and ED-TELECOM 98 919 - 924 1998年06月 [査読有り]
-
Context-Sensitive Filtering To Support Learning From Surfing
平嶋 宗, 松田 憲幸, 野本 豊裕, 豊田 順一
Proc. of ED-MEDIA98 and ED-TELECOM98 555 - 560 1998年06月 [査読有り]
-
Toward Context-Sensitive Filtering on WWW.
Tsukasa Hirashima, Noriyuki Matsuda, Toyohiro Nomoto, Jun'ichi Toyoda
Proceedings of WebNet 98 - World Conference on the WWW and Internet & Intranet ( AACE ) 1084 - 1085 1998年 [査読有り]
-
Context-sensitive Filtering for Browsing in Hypertext.
Tsukasa Hirashima, Noriyuki Matsuda, Toyohiro Nomoto, Jun'ichi Toyoda
Proceedings of the 3rd international conference on Intelligent user interfaces - IUI '98 ( ACM Press ) 119 - 126 1998年 [査読有り]
-
Context-Sensitive Filtering for Hypertext Browsing
Noriyuki Matsuda, Toyohiro Nomoto (担当区分: 筆頭著者 )
Information Systems And Technologies For Network Society: Proceedings Of The Ipsj International Symposium ( World Scientific ) 253 1997年09月 [査読有り]
-
An Instructional System for Behavior-Based Recursive Programming
松田 憲幸, 柏原 昭博, 平嶋 宗, 豊田 順一 (担当区分: 筆頭著者 )
Proc. of 8th World Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED-97) 325 - 330 1997年08月 [査読有り]
-
野本 豊裕, 松田 憲幸, 平嶋 宗, 豊田 順一
Proceedings of the workshop "Intelligent Educational Systems on the World Wide Web", 8th World Conference of the AIED Society pp. 40-46 1997年08月 [査読有り]
-
A Support Facility for Browsing in Hypertext based on Local Context
松田 憲幸, 辻本 昇平, 平嶋 宗, 豊田 順一 (担当区分: 筆頭著者 )
Proceedings of the Seventh International Conference on Human-Computer Interaction 42 1997年08月 [査読有り]
-
再帰プログラミングを対象とした問題の比較に基づく問題機能の実現
松田 憲幸, 柏原 昭博, 平嶋 宗, 豊田 順一 (担当区分: 筆頭著者 )
教育システム情報学会誌 = Transactions of Japanese Society for Information and Systems in Education ( 教育システム情報学会 ) 14 ( 2 ) 93 - 104 1997年07月 [査読有り]
-
松田 憲幸, 柏原 昭博, 平嶋 宗, 豊田 順一 (担当区分: 筆頭著者 )
電子情報通信学会論文誌. D-2, 情報・システム 2-情報処理 ( 電子情報通信学会 ) 80 ( 1 ) 326 - 335 1997年01月 [査読有り]
-
Information Filtering for Context-Sensitive Browsing.
Tsukasa Hirashima, Noriyuki Matsuda, Toyohiro Nomoto, Jun'ichi Toyoda
AI '97: Proceedings of the 10th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence: Advanced Topics in Artificial Intelligence ( Springer ) 379 - 388 1997年 [査読有り]
-
An Instructional System for Constructing Algorithms in Recursive Programming
Noriyuki Matsuda, Akihiro Kashihara, Tsukasa Hirashima, Jun'ichi Toyoda (担当区分: 筆頭著者 )
Advances in Human Factors/Ergonomics ( Elsevier ) 20 889 - 894 1995年 [査読有り]
書籍等出版物
-
人工知能学大事典
人工知能学会( 担当: 分担執筆, 担当範囲: 15-27 教育エージェント)
共立出版 2017年07月 ISBN: 9784320124202
-
ユビキタスコンピューティングと応用
( 担当: 共著, 担当範囲: 応用技術として、家庭調理記録のインデキシング技術を解説)
電気学会・通信教育会 2008年08月
Misc
-
「人工知能,IoTがもたらす新たな学習・教育・管理の促進」特集号発刊にあたって
松田憲幸 (担当区分: 筆頭著者 )
教育システム情報学会誌 37 ( 2 ) 71 - 72 2020年04月
-
多肢選択問題における誤選択肢の表層的類似性と深層的類似性
石橋 和樹, 松田 憲幸, 小川 修史, 平嶋 宗, 瀧 寛和
2016年度人工知能学会全国大会(第30回) ( 人工知能学会 ) 1C3-2 2016年06月
-
インタラクティブセッション(<特集>2015年度人工知能学会全国大会(第29回))
内海 慶, 原田 拓, 佐藤 敏紀, 松田 憲幸, Kei Uchiumi, Taku Harada, Toshinori Sato, Noriyuki Matsuda, 株式会社デンソーアイティーラボラトリ, 東京理科大学, LINE株式会社, 和歌山大学
人工知能 = journal of the Japanese Society for Artificial Intelligence 30 ( 6 ) 768 - 768 2015年11月
-
多肢選択問題における有意味誤選択肢の提案
松田 憲幸, 小川 修史, 平嶋 宗, 瀧 寛和
第29回人工知能学会全国大会論文集 ( 人工知能学会 ) 1E5-OS-11b-4 2015年05月
-
NIRSを利用した文章の肯定・否定に関する脳状態の識別
谷野 広祐, 瀬戸 勇記, 阿児 駿平, 阪上 慶二朗, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 曽我 真人, 瀧 寛和
第28回人工知能学会全国大会論文集 ( 人工知能学会 ) 1F4-OS-06a-5 2014年05月
-
インデックス脳におけるスナップ記憶と短間隔記憶について
瀧 寛和, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 曽我 真人, 安部 憲広
第24回人工知能学会全国大会予稿集1A4-1 ( 人工知能学会 ) JSAI2010 2010年06月
-
デッサン学習者の身体動作分析に基づく診断助言機能を持つデッサン学習支援環境
和田 隆人, 原 章訓, 古賀 俊廣, 曽我 真人, 松田 憲幸, 高木 佐恵子, 瀧 寛和, 吉本 富士市
第20回人工知能学会全国大会論文集 ( 人工知能学会 ) 2D2-1 2006年06月
-
辻達也, 北内隆寛, 高木佐恵子, 松田憲幸, 曽我真人, 瀧寛和, 岩崎慶, 吉本富士市
画像電子学会第224回研究会講演予稿 05 ( 07 ) 125 - 130 2006年03月
-
曽我 真人, 瀧 寛和, 松田 憲幸, 高木 佐恵子, 吉本 富士市, Masato Soga, Hirokazu Taki, Noriyuki Matsuda, Saeko Takagi, Fujiichi Yoshimoto
人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence ( 一般社団法人 人工知能学会 ) 20 ( 5 ) 533 - 540 2005年09月 [招待有り]
-
学習者のデッサン描画時における腕動作・視線・認識の分析
岩城朝厚, 前野浩孝, 六十谷伸樹, 中田早苗, 曽我真人, 松田憲幸, 高木佐恵子, 瀧寛和, 吉本富士市
第19回人工知能学会全国大会論文集 ( 人工知能学会 ) 2B1-02 2005年06月
-
用語解説「電子透かし」
松田憲幸 (担当区分: 筆頭著者 )
教育システム情報学会誌 255 - 255 2000年01月 [招待有り]
受賞(研究活動に関するもの)
-
論文編集活動感謝状
2019年05月 電子情報通信学会
-
論文賞
受賞者: 瀬田 和久, 崔 亮, 池田 満, 松田 憲幸, 岡本 真彦 2015年09月 教育システム情報学会 思考外化と知識共創によるメタ認知スキル育成プログラム ―大学初年次生を対象として―
-
Best Technical Design Paper Award Nominee
受賞者: 小川 修史, 松田憲幸, 平島宗, 瀧寛和 2011年 International conference on Computers in Education Knowledge Externalization Based on Differences of Solutions for Automatic Generation of Multiple-choice Question
-
優秀論文発表賞
受賞者: 平松宙祥, 内藤祐喜, 瀧 寛和, 松田憲幸, 中島二郎, 中村 正, 今川彰久, 松澤佑次 2003年 電気学会 オントロジーを利用した医療文献検索システム
講演・口頭発表等
-
両耳聴効果に基づく一側性難聴者への配慮を学ぶ教材の設計
福井淑紀, 武内龍伸, 松田憲幸
2024年度学生研究発表会・発表論文 2025年03月04日
-
看護実体験の振り返りによる実践的知識構築の分析
湯浅眞太, 松田憲幸, 武内龍伸, 池田満
日本教育工学会2024秋季全国大会 2024年09月
-
看護メタ思考を促す指導法に関する研究
松田憲幸 [招待有り]
島根県立大学看護教育学特論Ⅲ 2024年07月20日
-
なぞかけを構成する単語間の関連性の分析
本山 翔梧, 武内龍伸, 松田憲幸
2024年電子情報通信学会総合大会ISSジュニア&学生ポスターセッション, ISS-P-047 2024年03月07日
-
看護思考法教材デザインのための思考誤りの調査
松田憲幸, 湯浅眞太, 武内龍伸, 岡室優
日本医学看護学教育学会誌 2024年02月
-
和歌山におけるAIと看護の共存~思考の訓練~
松田憲幸 [招待有り]
第14回(2023年度)和歌山保健看護学会学術集会 2023年08月19日
-
看護業務における論理的思考の問題点の分析
松岡 翼斗, 松田 憲幸, 中山 雄貴, 森田 海, 池田 満
日本教育工学会2020年秋季全国大会 2020年09月12日 日本教育工学会
-
峠 貴文, 松田 憲幸, 田中 孝治, 池田 満
教育システム情報学会 JSiSE2019 第44回全国大会 P2-15 2019年09月 教育システム情報学会
-
病院看護における思考の振り返りを支えるライティングツールの設計
峠 貴文, 松田 憲幸, 田中 孝治, 池田 満
人工知能学会 先進的学習科学と工学研究会 ALST-85 2019年03月 人工知能学会
-
病院看護を対象とする思考法研修のための学習管理システムの設計
峠 貴文, 松田 憲幸, 田中 孝治, 池田 満
人工知能学会研究会資料 第84回 先進的学習科学と工学研究会 SIG-ALST-B802-05 2018年11月 人工知能学会
-
異文化理解における自問自答を通した信念解明ツールの開発
峠貴文, 松田憲幸
第43回教育システム情報学会全国大会,PC4:プレカンファレンス 2018年09月 教育システム情報学会
-
病院看護師による実践的知識の学習状態の分析を指向したライティングの分析
中山 貴之, 松田憲幸, 劉朝陽, 田中孝治, 池田満
人工知能学会 先進的学習科学と工学研究会 SIG-ALST-B508-07 2017年11月 人工知能学会
-
峠 貴文, 松田 憲幸, 瀬田 和久, 池田満
人工知能学会 先進的学習科学と工学研究会 SIG-ALST-B508-08 2017年11月 人工知能学会
-
大学病院の看護組織の研修における思考スキルの調査
松田憲幸, 中島仁喜, 陳 巍, 田中孝治, 池田 満
第7回知識共創フォーラム 2017年03月02日 知識共創フォーラム
-
信念対立解明ツールが思考過程に与える影響に関する予備研究〜階層ベイズモデルを用いて
京極真, 松田憲幸, 瀬田和久, 池田満
日本作業療法学会抄録集 2016年09月 日本作業療法学会
-
パフォーマンス表現を用いた看護職者メタ思考スキルの 自己評価データの考察
劉 朝陽, 田中 孝治, 陳 巍, 松田 憲幸, 池田 満
第41回教育システム情報学会全国大会 2016年08月 教育システム情報学会
-
ライティング指導者の添削思考を推定する 視線パターン分析支援システムの設計
中島 仁喜, 松田 憲幸, 劉 朝陽, 田中 孝治, 池田 満, 瀬田 和久, 林 佑
教育システム情報学会全国大会予稿集A5-3 2016年08月 教育システム情報学会
-
多肢選択問題における誤選択肢の表層的類似性と深層的類似性
石橋 和樹, 松田 憲幸, 小川 修史, 平嶋 宗, 瀧 寛和
2016年度人工知能学会全国大会(第30回) 2016年06月 人工知能学会
-
業務経験の思考を整頓する学び方の研修法
松田憲幸 [招待有り]
教育システム情報学会学会誌 2016年04月01日 教育システム情報学会
-
異文化理解における無自覚な信念の解明への関心を促す学習シナリオの開発
伊藤亜沙利, 松田憲幸, 小川泰右, 京極真, 瀬田和久, 池田満
第6回知識共創フォーラム 2016年03月13日 知識共創フォーラム
-
看護経験を書き表す学び方の学習における論理的な構造に注意を向ける学習環境の設計
鈴木貴之, 松田憲幸, 西山大貴, 陳巍, 田中孝治, 池田満
第6回知識共創フォーラム 2016年03月12日 知識共創フォーラム
-
看護学生のロールモデル形成におけるメタ認知に関する研究
水田真由美, 山田和子, 鍋田智広, 松田憲幸
第26回日本医学看護学教育学会学術学会 2016年03月12日 日本医学看護学教育学会
-
看護学生のロールモデル形成のための学習プログラムの検討
水田真由美, 鍋田智広, 山田和子, 松田憲幸
第25回日本医学看護学教育学会学術学会 2016年03月
-
多肢選択問題における誤選択肢の役割の調査
石橋和樹, 松田憲幸, 小川修史, 平嶋宗
第6回知識共創フォーラム 2016年03月 知識共創フォーラム
-
看護職者のパフォーマンス表現を用いたメタ思考スキルの自己評価項目の開発
劉 朝陽, 田中 孝治, 陳 巍, 池田 満, 松田 憲幸
第6回知識共創フォーラム 2016年03月 知識共創フォーラム
-
信念対立の内省的記述に対する批評活動を通じた看護知共創スキル育成プログラム
西山 大貴, 田中 孝治, 松田憲幸, 陳巍, 池田満
教育システム情報学会 2015年度学生研究発表会 2016年02月 教育システム情報学会
-
質問による思考トレーニングの授業実践
松田憲幸, 京極真, 瀬田和久, 池田満
日本教育工学会研究報告集 2015年10月 日本教育工学会
-
石橋 和樹, 小川 修史, 松田 憲幸, 平嶋 宗, 瀧 寛和
第40回教育システム情報学会全国大会講演論文集 2015年09月 教育システム情報学会
-
学習経験を活用したメタ思考の意識を促す学習デザイン
陳巍, 田中孝治, 崔亮, 松田憲幸, 池田満
日本教育工学会第31回全国大会講演論文集 2015年07月 日本教育工学会
-
多肢選択問題における有意味誤選択肢の提案
松田 憲幸, 小川 修史, 平嶋 宗, 瀧 寛和
第29回人工知能学会全国大会論文集 2015年05月 人工知能学会
-
中島仁喜, 松田憲幸, 瀧寛和, 崔亮, 田中孝治, 池田満
人工知能学会 第73回先進的学習科学と工学研究会 SIG-ALST-B403-17 2015年02月27日 人工知能学会
-
看護学生のロールモデルの実証的調査―臨地実習の経験が看護系大学生の学習目標の内容と達成のための自己調整に及ぼす影響―
鍋田 智広, 水田 真由美, 山田 和子, 松田 憲幸
日本医学看護学教育学会学会誌 2015年 日本医学看護学教育学会
-
思知プレイヤー:看護思考の吟味プロセス再生ツール
陳 巍, 崔 亮, 田中孝治, 松田憲幸, 池田 満
日本教育工学会第30回全国大会講演論文集 2014年09月19日 日本教育工学会
-
看護サービス思考スキルを育成するための議論における誘導的発言を促すカードゲームの開発
崔 亮, 神山資将, 田中孝治, 松田憲幸, 池田 満
日本教育工学会第30回全国大会 2014年09月19日 日本教育工学会
-
叶 秀征, 西山大貴, 田中孝治, 崔亮, 池田 満, 松田憲幸, 三浦浩一, 瀧 寛和
第39回教育システム情報学会全国大会論文集 2014年09月10日 教育システム情報学会
-
京谷 隆史, 陳 巍, 崔 亮, 松田 憲幸, 池田 満, 三浦 浩一, 瀧 寛和
第39回教育システム情報学会全国大会 2014年09月10日 教育システム情報学会
-
信念対立解明アプローチを基礎とした 異文化理解力涵養プログラムのためのシステム開発
辻川 達郎, 小川 泰助, 瀬田 和久, 池田 満, 松田 憲幸, 三浦 浩一, 瀧 寛和
第39回教育システム情報学会全国大会 2014年09月10日 教育システム情報学会
-
看護信念対立の内省的記述に対する批評活動を通じたメタ思考スキル学習
西山大貴, 叶 秀征, 田中孝治, 松田憲幸, 崔 亮, 陳 巍, 池田 満
第39回教育システム情報学会全国大会 2014年09月10日 教育システム情報学会
-
擬似力覚知覚時のNIRSとEEGによる脳活動分析
阪上慶二朗, 瀬戸勇記, 阿児駿平, 谷野広祐, 三浦浩一, 松田憲幸, 曽我真人, 瀧寛和
第39回教育システム情報学会全国大会予稿集 2014年09月 教育システム情報学会
-
陳 巍, 崔 亮, 田中孝治, 西山大貴, 松田憲幸, 池田 満
第39回教育システム情報学会全国大会論文集 2014年09月 教育システム情報学会
-
看護サービス学習を持続させるメタ思考力不足認識手法の開発
田中孝治, 崔 亮, 陳 巍, 松田憲幸, 池田 満
第39回教育システム情報学会全国大会予稿集 2014年09月 教育システム情報学会
-
NIRSを利用した文章の肯定・否定に関する脳状態の識別
谷野 広祐, 瀬戸 勇記, 阿児 駿平, 阪上 慶二朗, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 曽我 真人, 瀧 寛和
第28回人工知能学会全国大会論文集 2014年05月12日 人工知能学会
-
西山 大貴, 田中 孝治, 叶 秀征, 松田 憲幸, 崔 亮, 陳 巍, 池田 満
第28回 人工知能学会全国大会論文集3D3-1 2014年05月 人工知能学会
-
陳 巍, 崔 亮, 田中 孝治, 西山 大貴, 松田 憲幸, 池田 満
2014年度人工知能学会全国大会(第28回) 2014年05月 人工知能学会
-
崔 亮, 田中孝治, 陳 巍, 松田憲幸, 池田 満
信学技報, vol. 113, no. 377, ET2013-77 2014年01月11日 電子情報通信学会
-
田中孝治, 崔 亮, 陳 巍, 松田憲幸, 池田 満
信学技報, vol. 113, no. 377, ET2013-78 2014年01月 電子情報通信学会
-
京谷 隆史, 陳 巍, 崔 亮, 松田 憲幸, 池田 満, 瀬田 和久, 瀧 寛和
第29回日本教育工学会大会講演論文集 2013年09月21日 日本教育工学会
-
スキル学習支援のための疑似力覚生起時の脳波周波数分析 (教育工学)
阪上 慶二朗, 瀬戸 勇記, 阿児 駿平, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和
電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報 2013年05月26日 一般社団法人電子情報通信学会
-
脳波を利用した意思判断における選択状態の分析
瀬戸 勇記, 阿児 駿平, 賀集 貴也, 坂上 智規, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 尾花 弘章
電気学会研究会資料. IIS, 次世代産業システム研究会 = The papers of Technical Meeting on Innovative Industrial System, IEEE Japan 2013年03月18日
-
脳波の周波数解析に基づく力覚タスクの分類
尾花 弘章, 阿児 駿平, 賀集 貴也, 坂上 智規, 瀬戸 勇記, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 次世代産業システム研究会 = The papers of Technical Meeting on Innovative Industrial System, IEEE Japan 2013年03月18日
-
看護系大学生のロールモデルに関する研究 -ロールモデル選択への自己への焦点化の影響-
鍋田智広, 水田真由美, 山田和子, 松田憲幸
日本発達心理学会第24回大会, P2-100 2013年03月 日本発達心理学会
-
組織学習ロードマップによる医療サービスの質向上への継続的取り組み
崔 亮, 神山 資将, 池田 満, 岡室 優, 松田 憲幸
第14回日本医療マネジメント学会学術総会 2012年10月12日 日本医療マネジメント学会
-
野口 宗之, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 次世代産業システム研究会 = The papers of Technical Meeting on Innovative Industrial System, IEEE Japan 2012年03月16日
-
牛窓 裕貴, 松田 憲幸, 三浦 浩一, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 次世代産業システム研究会 = The papers of Technical Meeting on Innovative Industrial System, IEEE Japan 2012年03月16日 電気学会
-
形状モデルを用いない3次元視覚によるロボットハンドのための把持点検出に関する研究
平田 雅也, 三浦 浩一, 中村 恭之, 呉 海元, 富田 文明, 西 卓郎, 松田 憲幸, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 次世代産業システム研究会 = The papers of Technical Meeting on Innovative Industrial System, IEEE Japan 2011年03月18日 電気学会
-
感染型ルーチングにおけるメッセージの複製数に基づくバッファリング手法
藤原 教嗣, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 次世代産業システム研究会 = The papers of Technical Meeting on Innovative Industrial System, IEEE Japan 2011年03月18日 電気学会
-
間取り図清書作業支援の誤り発見診断機能の検討
堀田 和宏, 松田 憲幸, 三浦 浩一, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 次世代産業システム研究会 = The papers of Technical Meeting on Innovative Industrial System, IEEE Japan 2011年03月18日 電気学会
-
定期試験における採点支援のための採点モデリング
金岡 健史, 松田 憲幸, 三浦 浩一, 瀧 寛和
教育システム情報学会第35回全国大会講演論文集、27-C2-4 2010年08月26日 教育システム情報学会
-
医療サービス教育のためのケースメソッドの設計-医療者の思考モデルの表現法について-
藤井 正基, 崔 亮, 大澤 郁恵, 池田 満, 鍋田智広, 松田憲幸
教育システム情報学会研究報告 2010年07月 教育システム情報学会
-
インデックス脳におけるスナップ記憶と短間隔記憶について
瀧 寛和, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 曽我 真人, 安部 憲広
第24回人工知能学会全国大会予稿集1A4-1 2010年06月01日 人工知能学会
-
アドホックネットワークにおけるメッセージフェリーのためのクラスタリングを用いたルート構築
西 大輔, 三浦 浩一, 瀧 寛和, 松田 憲幸
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2010年03月15日
-
アドホックネットワークにおける消費電力削減のためのデータサイズを考慮したキャッシング方式
安井 涼, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2010年03月15日
-
守田 義宗, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 三浦 浩一
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2010年03月15日 電気学会
-
Real time interpolation of haptic information using case base
T. Toki, H. Taki, H. Miura, N. Matsuda, M. Soga, N. Abe
AROB2010 2010年02月01日 International Society of Artificial Life And Robotics
-
認識・行動選択・行動の各段階の学習を支援するスキル学習支援環境 ‐デッサン描画スキル学習支援を例として‐
曽我真人, 松田憲幸, 瀧寛和
第34回教育システム情報学会全国大会ワークショップWD-2 2009年08月 教育システム情報学会
-
表象と表象のない知識の相互作用による問題解決-インデキシング脳の考察-
瀧 寛和, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 曽我 真人, 安部 憲広
人工知能学会全国大会論文集3C4-2 2009年06月01日
-
スケッチ学習における概略形状から詳細形状への描画誘導と診断助言機能の構築と学習支援効果の検証
曽我 真人, 栗山 翔太, 床井 浩平, 松田 憲幸, 瀧 寛和
第23回人工知能学会全国大会論文集 2009年06月 人工知能学会
-
小倉 一孝, 西田 好宏, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 安部 憲広
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2009年03月23日 電気学会
-
アドホックネットワークにおけるキャッシング技術について
三浦 浩一, 松田 憲幸, 内尾 文隆, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2009年03月23日
-
概略形状から詳細形状への描画誘導時に診断助言機能を持たせたデッサン学習支援システム
栗山 翔太, 曽我 真人, 松田 憲幸, 瀧 寛和
情報処理学会シンポジウム論文集 インタラクション2009 2009年02月 情報処理学会
-
モチーフの構図・形状詳細化の過程を考慮したデッサン学習支援環境
栗山 翔太, 曽我 真人, 松田 憲幸, 瀧 寛和
電子情報通信学会技術研究報告. ET, 教育工学 2008年09月13日 一般社団法人電子情報通信学会
-
概略形状から詳細形状への描画誘導機能をもつデッサン学習支援環境
栗山 翔太, 曽我 真人, 松田 憲幸, 瀧 寛和
教育システム情報学会全国大会講演論文集 2008年08月01日 教育システム情報学
-
瀧 寛和, 曽我 真人, 松田 憲幸, 三浦 浩一, 安部 憲広, 堀 聡
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2008年07月18日
-
身体知伝達のための例示の生成
瀧寛和, 曽我真人, 松田憲幸, 三浦浩一, 堀聡, 安部憲広
第22回人工知能学会全国大会論文集 2008年06月01日
-
質疑応答の概念辞書を駆使した遠隔指導支援システムの設計
坂本佳寿真, 小川修史, 松田憲幸, 三浦浩一, 瀧寛和, 堀聡, 安部憲広
第22回人工知能学会全国大会論文集 2008年06月 人工知能学会
-
ウェッブ推薦システムにおける概念継承を駆使した知識編集機能の設計
三木 崇史, 小川 修史, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2008年03月17日
-
RF-IDを用いた災害時の誘導と追跡
大杉 正敏, 高梨 郁子, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 堀 聡, 安部 憲広
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2008年03月17日 電気学会
-
無線センサーデバイスを用いたユビキタス震度計
嶋崎 庸介, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 内尾 文隆, 塚田 晃司, 瀧 寛和
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2008年03月17日 電気学会
-
2P1-E12 館内移動用車椅子ロボットシステムの開発 : 位置情報検出機構(医療・福祉ロボティクス・メカトロニクス)
三輪 昌史, 余村 正人, 松田 憲幸, 橋爪 賢次郎
ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2008年 一般社団法人 日本機械学会
-
教え方の熟練を指向した概念辞書と分析エンジン
松田憲幸, 表武史, 今中武, 池田満, 瀧寛和
人工知能学会先進的学習科学と工学研究会資料 2007年11月 人工知能学会
-
角谷 知恵美, 塩路 有理, 村松 由美子, 小泉 美穂, 松田 憲幸, 服部 園美
看護情報研究会論文集 : JAMI-NS 2007年07月16日 日本医療情報学会看護部会
-
デッサン学習者の視線と動作の分析と学習支援環境への応用
斎藤 洋志, 古賀 俊廣, 前野 浩孝, 和田 隆人, 曽我 真人, 松田 憲幸, 高木 佐恵子, 瀧 寛和, 吉本 富士市
第21回人工知能学会全国大会論文集 1H3-3 2007年06月 人工知能学会
-
学生自主創造科学センターにおける入退室管理システムへのRFIDタグ組み込み方法の検討
藤垣元治, 松田憲幸, 太田貴之, 谷脇すずみ
第2回多分野交流研究会, 日本実験力学会 2007年04月 日本実験力学会
-
トランスダクティブ学習を利用した偏りのあるデータのマイニング手法
小櫻 茂樹, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 堀 聡, 安部 憲広
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2007年03月20日
-
運動学習のためのロボットハンドによる監視効果の実験
北内 隆寛, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 堀 聡, 安部 憲広
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2007年03月20日
-
古賀俊廣, 和田隆人, 前野浩孝, 曽我真人, 松田憲幸, 高木佐恵子, 瀧寛和, 吉本富士市
人工知能学会研究会資料 第49回的学習科学と工学研究会 SIG-ALST 2007年03月18日 人工知能学会
-
古賀 俊廣, 和田 隆人, 前野 浩孝, 曽我 真人, 松田 憲幸, 高木 佐恵子, 瀧 寛和, 吉本 富士市
情報処理学会シンポジウム論文集 2007年03月01日
-
LEARNING ENVIRONMENT WITH ADAPTIVE ADVICE FOR NOVICES' COLORED SKETCHES OF FRUITS
Takagi Saeko, Matsuda Noriyuki, Soga Masato, TAKI Hirokazu, YOSHIMOTO Fujiichi
電子情報通信学会技術研究報告. IE, 画像工学 2007年01月03日 一般社団法人電子情報通信学会
-
和歌山大学学生自主創造科学センターにおける既存の入退室管理システムへのRFIDタグの組み込み手法 ([日本実験力学会]2007年度年次講演会)
藤垣 元治, 谷脇 すずみ, 松田 憲幸
日本実験力学会講演論文集 2007年 日本実験力学会
-
腕動作と道具状態のモニタリングによる助言が可能なデッサン学習支援環境
前野浩孝, 古賀俊廣, 曽我真人, 松田憲幸, 高木佐恵子, 瀧寛和, 吉本富士市
教育システム情報学会2006年度特集研究会論文集 2006年12月01日 教育システム情報学会
-
看護行為の概念辞書を用いた看護支援システムの設計構想 (テーマ:先進的なe-Learning技術および一般)
松田 憲幸, 遠藤 聖彦, 瀧 寛和
先進的学習科学と工学研究会 2006年10月28日 人工知能学会
-
デッサン学習者の視線分析とデッサン学習支援システムへの応用
斎藤洋志, 曽我真人, 松田憲幸, 高木佐恵子, 瀧 寛和, 吉本富士市
第31回教育システム情報学会全国大会 2006年08月01日
-
ユビキタスデバイスを用いた屋内位置検出
三浦浩一, 坂本純一, 瀧寛和, 松田憲幸
電気学会産業応用部門大会講演論文集 2006年08月01日 電気学会
-
透視図法に基づいた描画スキル学習支援システムの構築
小路口 義丈, 曽我 真人, 松田 憲幸, 高木 佐恵子, 瀧 寛和, 吉本 富士市
第31回教育システム情報学会全国大会講演論文集B7-7 2006年08月 教育システム情報学会
-
デッサン学習者の身体動作分析に基づく診断助言機能を持つデッサン学習支援環境
和田 隆人, 原 章訓, 古賀 俊廣, 曽我 真人, 松田 憲幸, 高木 佐恵子, 瀧 寛和, 吉本 富士市
第20回人工知能学会全国大会論文集 2006年06月07日 人工知能学会
-
工業用ロボットハンドのティーチングの分析
北内隆寛, 小川修史, 松田憲幸, 三浦浩一, 瀧寛和, 堀聡, 安部憲広
第20回人工知能学会全国大会 2006年06月07日
-
語彙の階層構造に基づく申請書の自動記入
三木崇史, 小川修史, 松田憲幸, 三浦浩一, 瀧寛和, 堀聡, 安部憲広
第20回人工知能学会全国大会 2006年06月01日 人工知能学会
-
ブログ検索のためのブログ記事ネットワーク構築に関する研究
宗田 瞬, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 安部 憲弘, 堀 聡
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2006年03月14日 電気学会
-
看護計画の編集を支えるオントロジーの重ね合わせパターンの導出法
遠藤 聖彦, 小川 修史, 松田 憲幸, 三輪 昌史, 三浦 浩一, 瀧 寛和, 温 忍, 森 久美子, 杭ノ瀬 結子, 前田 悦子
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2006年03月14日 電気学会
-
自閉症児を対象としたデジタル教材オーサリングシステム : 調整可能な教材テンプレートの提案
小川 修史, 松田 憲幸, 三浦 浩一, 瀧 寛和, 堀 聡, 安部 憲広
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2006年03月14日 電気学会
-
小櫻 茂樹, 小川 修史, 三浦 浩一, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 安部 憲広
電気学会研究会資料. IIS, 産業システム情報化研究会 2006年03月14日 電気学会
-
辻達也, 北内隆寛, 高木佐恵子, 松田憲幸, 曽我真人, 瀧寛和, 岩崎慶, 吉本富士市
画像電子学会第224回研究会講演予稿 2006年03月
-
瀧 寛和, 松田 憲幸, 安部 憲広
情報処理学会研究報告 = IPSJ SIG technical reports 2006年01月26日 情報処理学会
-
三浦 浩一, 坂本 純一, 瀧 寛和, 松田 憲幸, 安部 憲広, 堀 聡
情報処理学会研究報告. DBS,データベースシステム研究会報告 2006年01月26日 一般社団法人情報処理学会
-
321 館内移動用車椅子ロボットシステム(S83 医療・福祉のためのロボットシステム,S83 医療・福祉のためのロボットシステム)
貝野 陽一, 三輪 昌史, 松田 憲幸, 橋爪 賢次郎
年次大会講演論文集 2006年 一般社団法人 日本機械学会
-
デッサン描画時の視線分析と準リアルタイムアドバイス機能を有するデッサン学習支援システムへの応用
岩城朝厚, 前野浩孝, 曽我真人, 松田憲幸, 高木佐恵子, 瀧 寛和, 吉本富士市
人工知能学会先進的学習科学と工学研究会(第45回)(ALST-45) 2005年11月 人工知能学会
-
学習者のデッサン描画時における腕動作・視線・認識の分析
岩城朝厚, 前野浩孝, 六十谷伸樹, 中田早苗, 曽我真人, 松田憲幸, 高木佐恵子, 瀧寛和, 吉本富士市
第19回人工知能学会全国大会論文集 2005年06月 人工知能学会
-
曽我真人, 松田憲幸, 高木佐恵子, 瀧寛和, 岩城朝厚, 辻達也, 大西隆裕, 吉本富士市
情報処理学会HI研究会 インタラクション2005, インタラクティブセッションA-104 2005年02月 情報処理学会
-
松田 憲幸, 飯田 将人, 三浦 浩一, 内尾 文隆, 内藤 敦士, 北村 義弘, 三明 道頼, 瀧 寛和
電子情報通信学会技術研究報告. ET, 教育工学 2004年12月18日 一般社団法人電子情報通信学会
-
初心者のための鉛筆デッサン学習支援システムー陰影指導への拡張ー
辻 達也, 坂口 仁美, 高木 佐恵子, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 曽我 真人, 岩崎 慶, 吉本 富士市
情報処理学会関西支部 支部大会 2004年10月 情報処理学会
-
演習授業中の質疑を記録する blog 概念を用いたツールの活用
松田 憲幸, 原田 勝行, 平嶋 宗, 瀧 寛和
日本教育工学会大会講演論文集 2004年09月23日
-
データマイニングにおけるたんぱく質のカスケード発見
内藤祐喜, 三浦浩一, 松田憲幸, 瀧 寛和, 安部憲広, 堀 聡
電気学会 産業システム情報化研究会 IIS-04-11 2004年06月 電気学会
-
情報処理環境のユビキタス機器による自動構成
梶本貴幸, 三浦浩一, 松田憲幸, 瀧 寛和, 安部憲広, 堀 聡
電気学会 産業システム情報化研究会 IIS-04-10 2004年06月 電気学会
-
携帯文書合成配信システム
飯田将人, 三浦浩一, 松田憲幸, 内尾文隆, 瀧 寛和, 安部憲広, 堀 聡
電気学会 産業システム情報化研究会 IIS-04-12 2004年06月 電気学会
-
北岡 大輔, 松田 憲幸, 平島 宗, 瀧 寛和
電子情報通信学会技術研究報告. ET, 教育工学 2003年09月20日 一般社団法人電子情報通信学会
-
Action Representation Web
松田 憲幸, 瀧 寛和, 安部 憲広
Proc. of the 6th SANKEN (ISIR) Int. Symposium 2003年03月
-
平松宙祥, 内藤祐喜, 瀧 寛和, 松田憲幸, 中島二郎, 中村 正, 今川彰久, 松澤佑次
電気学会 産業システム情報化研究会 IIS-03-21 2003年03月 電気学会
-
小川 修史, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 安部 憲広
電子情報通信学会技術研究報告. ET, 教育工学 2002年10月11日 一般社団法人電子情報通信学会
-
果樹育成の為のレトロフィットエージェント
田尻久幸, 内尾文隆, 張 勇, 松田憲幸, 瀧 寛和
電気学会 産業システム情報化研究会 IIS-02-4 2002年03月 電気学会
-
知的情報検索と文書の構造化を利用したスライドプレゼンテーション
水谷俊介, 松田憲幸, 瀧 寛和, 安部憲広, 堀 聡
電気学会 産業システム情報化研究会 IIS-02-9 2002年03月 電気学会
-
瀧 寛和, 松田 憲幸, 福井 透, 安部 憲広, 堀 聡
電子情報通信学会技術研究報告. KBSE, 知能ソフトウェア工学 2002年01月17日 一般社団法人電子情報通信学会
-
張 勇, 瀧 寛和, 松田 憲幸, 内尾 文隆, 安部 憲広, 堀 聡, 亀岡 孝治, 井口 信和
農業機械学会誌 2002年 The Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers
-
田尻 久幸, 内尾 文隆, 張 勇, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 井口 信和, 亀岡 孝治
農業機械学会誌 2002年 The Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers
-
調理の記録とレシピの自動対応付けツールの開発 (テーマ:「一般」および「情報の可視化と知識マネジメント」)
白藤 純, 松田 憲幸, 瀧 寛和
知的教育システム研究会 2001年09月29日 人工知能学会
-
Simulation based Reasoning for planning expert systems
張 勇, 瀧 寛和, 松田 憲幸, 堀 聡, 安部 憲広
Proc. of Workshop on Web Intelligence and Software Engineering, SIG-KBSE, IEICE 2001年08月24日 一般社団法人電子情報通信学会
-
オーサリングツールを利用した教育・学習ログの活用の構想 (特集 HAI(Human-Agent Interaction)および一般発表) -- (一般セッション)
松田 憲幸, 白藤 純, 瀧 寛和
知識ベ-スシステム研究会 2001年07月05日 人工知能学会
-
インフォメーションマッチメーキングサーバーによる情報流通基盤
林田高志, 松田憲幸, 瀧 寛和
電気学会 産業システム情報化研究会 IIS-01-5 2001年01月19日 電気学会
-
208 設計ドキュメントの再利用を考慮した設計制約の表現と管理(設計知識管理(2))
瀧 寛和, 松田 憲幸, 吉岡 克浩, 堀 聡, 安部 憲広
設計シンポジウム講演論文集 2001年 "日本機械学会, 精密工学会"
-
拡張現実感による全方位画像の為の情報提供システム (テーマ 「オントロジー活用の実際、産業応用」および一般)
吉岡 克浩, 松田 憲幸, 瀧 寛和
知識ベ-スシステム研究会 2000年11月17日 人工知能学会
-
頼光 正典, 松田 憲幸, 瀧 寛和, 安部 憲広
電子情報通信学会技術研究報告. AI, 人工知能と知識処理 2000年07月12日 一般社団法人電子情報通信学会
-
文脈情報に基づくブラウジング支援 : www上での実装
野本 豊裕, 松田 憲幸, 平嶋 宗, 豊田 順一
人工知能学会全国大会論文集 = Proceedings of the Annual Conference of JSAI 1998年06月16日
-
Visual Basicにおけるプログラミング環境
松田 憲幸
教育システム情報学会誌 = Transactions of Japanese Society for Information and Systems in Education 1998年01月01日 教育システム情報学会
-
文脈情報に基づくブラウジング支援 : Context Sensitive Filtering
野本 豊裕, 松田 憲幸, 平嶋 宗, 豊田 順一
人工知能学会全国大会論文集 = Proceedings of the Annual Conference of JSAI 1997年06月24日
-
文脈情報に基づくブラウジング支援 : ブラウンジング履歴の分析
松田 憲幸, 野本 豊裕, 平嶋 宗, 豊田 順一
人工知能学会全国大会論文集 = Proceedings of the Annual Conference of JSAI 1997年06月24日
-
文脈情報を用いたブラウジング支援 : Web上での実装とその実験的評価
辻本 昇平, 松田 憲幸, 平嶋 宗, 豊田 順一
人工知能学会全国大会論文集 = Proceedings of the Annual Conference of JSAI 1997年06月24日
-
ハイパ-テキストにおけるサ-フィング支援のためのユ-ザモデルとフィルタリング (知的教育システム研究会(第18回)テ-マ:一般)
平嶋 宗, 松田 憲幸, 豊田 順一
知的教育システム研究会 1997年05月 人工知能学会
-
プログラミングにおける再帰概念の形成の支援を行う教育システムの開発
松田憲幸, 柏原 昭博, 平嶋 宗, 豊田 順一
信学技報 1994年 一般社団法人電子情報通信学会
-
Prologプログラムを対象としたスキーマの獲得支援方法について
松田 憲幸, 柏原 昭博, 平嶋 宗, 豊田 順一
電子情報通信学会技術研究報告. KBSE, 知能ソフトウェア工学 1993年09月14日 一般社団法人電子情報通信学会
-
プログラム間の差異を利用したプログラム理解支援 : Prologを対象とした差異の抽出メカニズム
松田 憲幸, 柏原 昭博, 平嶋 宗, 豊田 順一
人工知能学会全国大会論文集 = Proceedings of the Annual Conference of JSAI 1993年07月20日 人工知能学会
研究交流
-
看護思考促進モデルの構築
2019年04月-継続中共同研究
-
運動スキルの言語化
2015年04月-2018年03月共同研究
-
マルチコプータ運用管理モデルの構築
2015年04月-2016年03月共同研究
-
ロールモデルを用いた看護教育プログラムの開発
2015年04月-2016年03月共同研究
-
メタ認知促進法の開発
2015年04月-2016年03月共同研究
-
概念の峻別とオントロジー構築法の調査研究
2007年04月-2008年03月共同研究
-
アグリバイオ遺伝子解析に役立つデータマイニング手法の研究開発
2004年04月-2005年03月共同研究
科学研究費
-
実践的知識のための思考語いに基づく研修法の構築
2022年04月-2027年03月基盤研究(B) 代表
-
誤り概念の体系に基づく看護思考法診断学習支援システムの構築
2018年04月-2022年03月基盤研究(B) 代表
-
認知科学的分析に基づくインタラクションサイクルモデルを礎としたスキル学習支援環境
2017年04月-2022年03月基盤研究(B) 分担
-
論理的分析を主軸とした批判的思考力育成モデルの構築
2017年04月-2021年03月基盤研究(B) 分担
-
身体動作の描写に基づいた意識の言語化支援と身体スキル獲得のための意識ベースの構築
2016年04月-2019年03月基盤研究(B) 分担
-
認知状態の脳活動分析を利用したスキル学習支援システムの研究
2015年04月-2018年03月基盤研究(B) 分担
-
看護組織の知識創造における考え方の語りによるリーダー育成法の実証
2014年04月-2017年03月挑戦的萌芽研究 代表
-
メタ認知スキルの形成を目的とした経験学習プログラムの設計支援
2014年04月-2017年03月基盤研究(B) 分担
-
メタ認知的アプローチによるロールモデルを用いた看護教育プログラムの開発
2014年04月-2017年03月基盤研究(C) 分担
-
感覚受容・抑制プロテクターを利用した技能教育システムの研究
2014年04月-2017年03月挑戦的萌芽研究 分担
-
患者中心の看護サービス技能の指導法の実証
2013年04月-2016年03月基盤研究(B) 代表
-
ロールモデルの実証的調査に基づく看護教育プログラムの開発
2012年04月-2014年03月挑戦的萌芽研究 分担
-
実践の物語化による病院看護サービスの熟達を支えるオントロジー駆動分析エンジン
2010年04月-2013年03月基盤研究(B) 代表
-
多様な学習形態を統合するコンテキストアウェア・コンポーネントアーキテクチャ
2010年04月-2013年03月基盤研究(B) 分担
-
シナブス可塑性を学習するニューラルネットワークの研究
2007年04月-2010年03月萌芽研究・萌芽的研究 分担
-
認識と動作の分析に基づくスキル学習支援環境の構築
2007年04月-2010年03月基盤研究(B) 分担
-
看護の技の伝承を目的としたe-learningシステムの構築
2007年04月-2010年03月基盤研究(B) 分担
-
絵画学習初心者のためのデッサン学習支援システムの構築
2004年04月-2007年03月基盤研究(B) 分担
-
量子重ね合わせ状態基づくユビキタスコンピューティング環境モデルの研究
2004年04月-2007年03月萌芽研究・萌芽的研究 分担
-
教育デジタル・コンテンツを用いた授業を対象とした授業活動モデルの生成技術の解明
2003年04月-2005年03月若手研究(B) 代表
-
仮想実験環境にける定性推論の技法を用いた認知的葛藤の制御
1997年04月-1999年03月基盤研究(B) 分担
公的資金(他省庁、省庁の外郭団体、地方自治体等)
-
平成23年度静岡大学電子工学研究所共同研究プロジェクト
2011年04月-2012年03月代表
-
平成22年度静岡大学電子工学研究所共同研究プロジェクト
2010年04月-2011年03月代表
-
平成21年度 静岡大学電子工学研究所 共同研究プロジェクト
2009年04月-2010年03月代表
-
治療概念スキーマによる知的病診連携システムの研究開
2001年04月-2002年03月分担
-
実地医家向け糖尿病治療支援システムの開発
2000年04月-2001年03月分担
財団・企業等との共同研究、受託研究、学術指導等
-
分散型IDの活用が社会に及ぼす影響に関する研究
2023年03月-2024年03月共同研究 分担
-
ドローン画像解析システムの研究
2021年02月-2022年02月共同研究 代表
公開講座等の講師、学術雑誌等の査読、メディア出演等
-
探究学習の指導
2025年05月08日-2025年10月30日大阪府立河南高等学校
-
査読
2024年11月01日-2025年01月30日情報処理学会
-
教授
2024年07月20日公立大学法人島根県立大学
-
学生支援プロジェクトの講師
2024年02月29日和歌山市役所
-
生涯学習市民講座
2024年01月30日和歌山大学
-
講師
2023年11月10日和歌山県立向陽高等学校・中学校
-
和歌山大学消費生活協同組合 理事
2022年05月25日-2025年05月24日和歌山大学消費生活協同組合
-
学会誌編集委員会 幹事
2019年04月-継続中教育システム情報学会
-
先進的学習科学と工学研究会 専門委員
2019年04月-継続中人工知能学会
-
教育工学研究会 専門委員、および、常任査読委員
2019年04月-継続中電子情報通信学会
-
社会人向け先端技術教育講座
2019年04月和歌山大学
-
第27回わかやまテクノ・ビジネスフェア わかやま発技術シーズ発表会
2018年04月わかやま産業振興財団/和歌山県/和歌山情報サービス産業協会
-
特集号編集委員
2017年04月-2020年03月電子情報通信学会和文誌D
-
編集委員会委員
2015年04月-継続中教育システム情報学会
-
英文誌編集委員
2015年04月-2020年03月電子情報通信学会英文誌D
-
査読
2015年04月-2016年03月Journal of Computers in Education
-
編集査読委員
2014年04月-継続中情報処理学会論文誌
-
査読
2014年04月-継続中The journal Research and Practice in Technology Enhanced Learning
-
特集号編集委員
2014年04月-継続中人工知能学会論文誌特集号
-
地域連携・生涯学習センター土曜講座
2014年04月地域連携・生涯学習センター
-
特集号編集委員
2013年04月-2015年03月電子情報通信学会
-
公開体験学習会
2012年04月和歌山大学学生自主創造科学センター
-
オープンキャンパス
2012年04月和歌山大学
-
公開体験学習会
2010年04月和歌山大学学生自主創造科学センター
-
査読
2008年04月-2016年03月教育システム情報学会
-
The Asia-Pacific Society for Computers in Education, International Conference on Computers in Education
2008年04月-2016年03月査読
-
査読
2008年04月-2016年03月日本教育工学会
-
メディア出演等
2007年12月東京商工リサーチ
-
講演講師
2007年11月和歌山県立新宮高等学校
-
メディア出演等
2002年07月読売新聞
-
メディア出演等
2002年07月日本経済新聞
-
メディア出演等
2002年05月日刊工業新聞
学協会、政府、自治体等の公的委員
-
編集委員会査読委員
2025年06月05日-2026年06月03日電子情報通信学会
-
委員
2015年04月-2020年03月電子情報通信学会
-
運営委員
2015年04月-2019年03月31日教育システム情報学会関西支部
-
研究会幹事
2014年04月-2017年03月人工知能学会
-
Financial Co-Chair
2014年04月-2016年03月The “11th International Conference on Knowledge Management” (ICKM2015)
-
委員
2014年04月-2015年04月人工知能学会
-
副委員長
2014年04月-2015年03月教育システム情報学会
-
LOCAL ORGANIZING COMMITTEE MEMBER
2014年04月-2014年12月Asia-Pacific Society for Computers in Education, The 22nd International Conference on Computers in Education
-
Program Committee Member
2010年01月-2010年12月The 18th International Conference on Computers in Education
-
特集号編集委員会委員
2009年12月-2010年12月日本教育工学会
-
Program Committee
2007年02月-2007年07月the IADIS Interfaces and Human Computer Interaction 2007 Conference
-
Implementaion Committee
2007年01月-2007年11月APSCE (Asia-Pacific Society for Computers in Education)
-
特集号編集委員
2006年12月-2007年12月教育工学会
-
編集委員
2004年04月-2008年03月教育システム情報学会
その他の社会活動
-
オンライン模擬授業
2023年07月05日和歌山県立日高高等学校
-
オンライン模擬授業
2022年12月23日和歌山県立橋本高等学校
-
模擬授業
2022年12月17日初芝橋本高等学校
-
模擬授業
2022年11月04日和歌山県立向陽高等学校
-
和歌山大学生協理事会
2015年04月-継続中その他
-
飾り傘をおろう!
2012年04月-2013年03月その他



